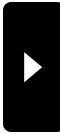ルーコ水野のソーシャルマーケティング1年生【豊田市Facebook導入】 › SNSお役立ちネタ
豊田市のルーコでWebの仕事をする水野が、モトハウス248さまとのお仕事の中での発見をお伝えしていきます。※当ブログは更新終了しましたー

バイク屋さんのFacebook活用法「納車のお客さん+スケッチブック」
こんにちは、ミズノです!今日はちょっとした小ネタをお届けします。
モトハウスさんのFacebookページの投稿を見ていて、いいな〜と思うものがあったので、そのご紹介です。
それがこちら!!
(クリックで実際の画面へ!)
やり方
納車のお客さんに、1.スケッチブックに一言メッセージを書いてもらう。2.スケッチブックを持ってもらいハイ、チーズ。3.それをFacebookにアップする。
といった流れですね。
スケッチブックのメッセージ内容に個性が出てます。表情も、満面の笑み〜無表情まで、何とも言えない哀愁を感じるものもあったり(笑)
また、わかりやすいように月ごとにひとつのアルバムとしてまとめられています。
ミズノ的ベスト3
個人的に気になったものをランキング形式でご紹介
第3位!!

好青年!いろんな思いメッセージを感じます。
第2位!!

メッセージと合わせて、はにかんだ笑顔がなんともよいですね。
第1位!!

そのままバイクのキャッチコピーになりそうな、爽やかな風を感じました。
まとめ
こんなFacebookの使い方いかがでしょうか?
お店の業種や個性によって、いろんな使い方がありますよね。Facebookページ運用の参考にしていただければ幸いです。
他にも、よいFacebookページの活用法がありましたら、ぜひ教えてくださいm(._.)m
街のバイク屋さんが「Facebook広告」で成果を出すには? について調べました。
こんにちは、ミズノです!今日はソーシャルな話題を取り上げます!

先日の打ち合わせで、お伝えしたとおり、ボタンがあれば何でも押したがりのおかんさん(笑)、「Facebook広告」 に興味アリとのことで、調べてみました。せっかくですので、みなさんにもお伝えしたいと思います。
Facebook広告とは?
文字通り、お金を払ってFacebook上に広告を出せるというものですが、調べていくと、種類がいろいろあり、特徴もそれぞれ違うようです。
3種類の広告
- 1.Facebook広告
- 2.Facebookスポンサー記事
- 3.ページ投稿の広告
どれを選ぶかにより、
- 何を宣伝するか(FBページ・投稿・ホームページ)
- 表示方法や表示される人
- 費用
などが、変わってくるようです。
下記サイトに、うまくまとめられていました。
Facebook広告の種類・出稿方法・ポイントまとめ!! | インバウンドマーケティング/Facebookアプリ Hivelocity ハイベロシティ
人づてに聞いた、ありがたい話
うちのスタッフが、あるセミナーで聞いたところによると、今Facebook広告をやるのはメリットが大きい!のだそうです。その理由をいくつか挙げると、
- いいねが資産として貯まっていく。(リスティングなどは貯まらない)
- 今は費用が安い(らしい)。みんなが使い出すと高くなる。
- 表示させるターゲットを細かく設定できる。
といったことがあるようです。さらに言うと、目にみえて成果があがるのでテンションがあがる、のだそう。(そうだといいなー)
Facebook広告で成果を出すには?
というように、いろいろ調べた結果、Facebook広告で成果を出すにはこんなことに注意すればよいと言えそうです。
- ターゲット層をしっかり見極めて、細かい設定をする。
- 宣伝するページの内容をしっかり作る。
- ABテスト(違う広告2つやってみて、いいほうを選ぶ)をやる。
せっかくお金をかけて宣伝するのだから、できるだけ効果が出せるようにしたいですね。
モトハウスさんの場合なら
実際に、モトハウスさんでやるならどんな風にしたらいいのか、と考えてみました。
- 作戦A(おてがるコース)
- 作戦B(じっくりコース)
と、2つプランを考えました。
作戦A(おてがるコース)
おてがるコースでは、いまあるFacebookページを、そのまま宣伝します。これなら、すぐにでもはじめることができますね。
作戦B(じっくりコース)
じっくりコースでは、まず「宣伝するページを作るところから」はじめます。ホームページやFBページをそのまま使うのではなく、「モトハウス248いいとこ取りページ」を作成してそれを宣伝しようという作戦です。
こちらの場合、ページを作る時間はかかりますが、同じだけの費用をかけて宣伝した場合を比べると、より効果がありそうです。
まとめ
ということで、どちらのコースかはおかんさんに聞いてみようと思います。(そもそも、広告をやるのかという話も含めて)
また進展がありましたら、お伝えしますね。
参考リンク
今回、調べた時にお世話になったサイトです。
- Facebookの広告(公式ページ)
- Facebook広告の活用法(公式ページ)
- キャンペーンの費用と予算 | Facebookヘルプセンター
- Facebook広告って何?どうやって出稿するの? | ソーシャルリクルーティングの世界
Facebookチェックインクーポンの作り方。
さてさて、最近この話題ばかりですね「チェックインクーポン」です。
先日モトハウスさんで打ち合わせをさせていただき、クーポンの内容が決定しました!
早速、登録をしてみたので、ご紹介いたします。
手順
まずは下ごしらえ。以前からこのブログで追いかけてきた、FBページとチェックインスポットの統合をしておく必要があります。
下ごしらえが完了していれば、管理画面に「クーポン」の項目が出てきますのでクリック。
続いて「チェックインクーポンを作成」をクリック。
続いて内容の入力。こんな画面です。
すると、実際にどんな画面が表示されるかを確認することができます。

そして、クーポンを作成とすると、完了!
といっても、ここから寝かせる時間が少しあるようです。
「承認待ち」 ということです。悪質なクーポンがないか、Facebookさんがチェックしているんでしょうね~。
チェックインクーポンの開始日を決める際には、クーポンの審査に最大7日かかることを考慮してください。
とのことでした。
細かい設定
クーポンの内容については、日本語で書ける内容であればなんでもOKのようですね(審査に通れば)。アイデア次第でいろんな可能性が広がるのではないかと思います。
そのほか、こんな設定があるようです。
- クーポンの発行期間
- 発行枚数
- 1人1回 or 24時間に1回
チェックインクーポンはどういいのか?
さて、チェックインクーポンを使うと、なにがどういいのか?
ということを簡単にご説明しますと・・
3方よし
- お客さん
-
チェックインするだけでなにかしらお得になるからうれしい!
- お客さんの友達
-
Facebookでお店のことやお得な情報を知れる!
- お店
-
新しい人に知ってもらえてうれしい!
というようなことだと思います。ざっくり過ぎますか?^^;
興味を持たれた方、ぜひチェックインクーポン作ってみてくださいね!
ちなみに・・・、気になるモトハウスのクーポンの内容は・・・お店に行って確かめてくださいね!!
Facebookチェックインクーポンを調べる。&考える。
こんにちは
前回、難題を解決して次の段階に進んでいるモトハウスさんとの取り組み。ようやくできるようになったチェックインクーポンをどんな内容にしましょう?というところに来ています。
他のお店はどんなクーポンを発行しているんだろう〜?というところで、少し調べてみました。
と、そのまえに。クーポンは2種類
まずは、おさらいからです。どうやら、Facebookのクーポンには2種類あるようですよ。
- フェイスブッククーポン
- チェックインクーポン
のふたつです。
違いは下記のサイトにうまくまとめてありました。
大きな違いは、その場にいかないと発行できないのがチェックインクーポン、そうでないのがFacebookクーポンですね。
今回はチェックインクーポンで考えています。
スマホを持ってモトハウスさんに来店し、Facebookでチェックイン!をすると発行されるということですね。
チェックインクーポン詳細
ではチェックインクーポンを少し掘り下げます。発行画面に進んでみるとこのような画面に。
クーポンの種類が4つから選べるようです。引用します。
- 一人用クーポン
-
お店にチェックインする個人顧客にお得な情報を提供しましょう。ディスカウントや購入者へのギフトなどに最適です。
- グループ用クーポン
-
友達同士が一緒にチェックインすると利用できるグループ用クーポンで、さらに大きなクチコミ効果を狙いましょう。
- ポイントクーポン
-
お店に一定回数チェックインすると利用できる、ポイントカードと同様のクーポンを提供して、リピーター顧客を獲得しましょう。
- チャリティクーポン
-
顧客がチェックインすると、指定したチャリティに寄付が実行されます。
というように、いろいろなパターンがあるようですね。
チェックインクーポン事例。いろいろ
さて、ここからはリンクの紹介でお茶をにごします^^;
世の中いろいろなアイデアでクーポンを発行されている方がいますね〜。
事例から見る効果的だと思う2パターン チェックイン機能は「店舗に入店してから使用する」ことが多いです。そのことを考慮すると、以下のパターンが効果的です。 1.チェックインすると付加価値のあるサービスを受けられる 2.リピーター獲得向けのサービスを提供する
なるほどなるほど。
こちらは、海外の事例がいろいろ掲載されていました。
H&M(ファッションブランド)20パーセントオフの提供
ですって!太っ腹!
コチラは変わりダネ。
サッカーの試合を観戦すると、すき家の牛丼が一杯プレゼントされるそうです。
企業の垣根を越えたコラボレーションですね〜。双方の理解とメリットがあれば、面白いモノが生まれそう。
モトハウスオリジナルクーポンを!!
そして・・・、情報は探せばできてきますが、他のマネじゃつまらない。それに、参考の事例は業種も違うし、置かれている状況も違いますしね。
モトハウス248のオリジナリティあふれるクーポンができたらいいな〜と思っています。そのあたり、おかんさんと一緒に考えていきます。
進展あり!FBページとチェックインスポットの統合。
こんにちは。前回のブログで少し予告していましたが、例のあの問題「Facebookページとチェックインスポットが統合できないよ〜(泣)」が、つ、ついに!解決しました!!
記事にしたのが9月の頭、その前から格闘ははじまっているので、足かけ5ヶ月←!
ブログやFacebookに書いたところ、いろいろな方からご意見をいただいたり、その節はお世話になりましたm(._.)m
Facebookさん、ちゃんとお仕事していただいているようです。。
ことの顛末
さて、時系列順にことの顛末を追ってみます。
※今回は画像をクリックすると拡大します!
ある日、モトハウス248FBページの管理画面に入ってみると、見なれないメッセージが!?
リンクをクリックして進んでみると・・
ページの住所変更ができるとのこと!
「よろしくお願いします!」とビックリマークをつけて送りました。
すると、例の憎きメッセージが消えて、無事住所が登録されました。ふう〜やれやれ。
その後は、ニイハチヨンサンさんの記事の通り、設定画面の「リソース」というところに入っていくと、重複しているページを統合というリンクが出ていました。
統合?と聞かれるのでもちろんYes!「Marge Page」をポチッと。
統合したい2つのページは以下の通り。
▼モトハウス248のFBページ
▼モトハウス248のチェックインスポット
ここでまた問題発生!!
統合依頼をしたはいいものの、しばらく経っても変化がみられません。
左のサイドバーにも、FBページ、チェックインスポットどちらも表示されています。
仕方ないので、再度申請してみます。(3〜4回やりました^^;)
その甲斐あってか・・・
突然Facebookの画面上にメッセージが!!(この間5日くらい)
「当選おめでとうございまーす!!!」くらいのインパクトがありました。(ちなみに、おかんさんの方でも表示されたようです)
ということで、無事Facebookページとチェックインスポットの統合ができたというわけです。ちゃんちゃん。
困っている方は、管理ページの「基本データ」をちょくちょくチェックしてみましょう。(申請は1回だけでもよかったかもしれません。。)
はて、なんのためだったか・・・?
さてさて、統合が目的みたいになってしまってますが、なぜ統合したかったのか?
クーポンが発行したかった
からなんですね〜。
このように、クーポン作成画面も無事表示されるようになりました。
クーポン内容は、おかんさんと相談中です。近日中に発行できるかと思いますので、お楽しみに!
Facebookで何を書いたらいいかわからない場合は?
こんにちは、ソーシャルマーケティング一年生のミズノです!
Facebookで何を書いたらいいかわからない
アカウントをとったはいいけど、なにもしていない
そんな方けっこういらっしゃるのではないでしょうか?

今度ブーログで行う「Facebook初心者講座」の参加希望者さんのアンケートや、お客さま、ブロガーさんとお話をしていても、そういった声はよく耳にします。
講習会の準備もかねて、調べたことがあるので少し書いておきます。
ブログとFacebook どっちに何を書く?
これを見て下さっている方はブーログをされている方が多いかと思います。Facebookをはじめるとなると、どっちに何を書こう??となってしまいがちかと思います。
そこでこのように考えてはどうでしょう?
誰に向けて書いているか?を意識してみる。
- Facebook→Facebookでつながっている友達
- ブログ→ブーログ友達&不特定多数の大勢の人
書く内容でわけてみる。
- Facebook→ちょっとした日々のできごと(記事はどんどん流れていく)
- ブログ→ちゃんと向き合って書く、ちょっとした「作品」みたいなもの。(貯まっていく・検索される)
機能的な部分でわけてみる。
- Facebookアルバム→写真をたくさんのせるのに便利。
- Facebookチェックイン→どこどこに行きましたorいます。
- Facebookタグ→誰々と一緒にいます。
- ブログ→文字の装飾や写真の配置などがある程度自由にできる。
- ブログ→検索で探されることがある。整理してリスト化できる。
このように、それぞれの特長がわかってくると、どちらに何を書いたらいいかわかってきますね。
もちろん、双方にリンクすることは簡単にできますので、やりやすい方で書いて、もう一方は告知だけというのも手かもしれません。
以前に書いた記事も参考になると思います、よろしければドウゾ。
また、直接話を聞きたい!という方は、ぜひ講習会にご参加ください。詳細はブーログ編集部のブログで!
肩書きに迷ったら聞いてみる。〜読者さんのコメントから
こんにちは、ソーシャルマーケティング1年生です。さて、今日は少し違った角度からお伝えしたいと思います。
前回の記事では、Facebookセミナーで教えていただいた「Facebookにはブランディングが大切ですよ」ということを書きました。
そうしたところ、ブーログ古参のブロガーさん「草野球チーム・自営隊 “隊長”こと“ジュエル足立”」さん(な、なんて名前!)から興味深いコメントをいただきました。
プロフィール写真お借りしました。こんなステキなネクタイをされているジュエル足立さん。
全文引用させていただきます。
こんにちは、Boo-logブロガー内で、一番「アヤシイ」感じの 草野球チーム・自営隊 “隊長”こと“ジュエル足立”です。
記憶に残してもらいやすい肩書きを作る
私はBoo-log参加当初から 『笑いの取れる宝石屋』を目指しているんですが 「アヤシイ」と「笑い」のベクトルの真逆に、宝石屋にとって一番大切な
【信用】
が、あるような気がするんですが・・・ だ・・・大丈夫ですよね?
つまり、セミナーの言葉を借りれば、ジュエル足立さんは『笑いの取れる宝石屋』ブランディングをされているということですね。
宝石を買おうと思う人の気持ち
ここで、「あ、それはですね、こういうことなんですよ!(ビシッ)」っと言いたいところですが・・・、正直的確な答えが出てきません。これはセミナーで勉強したからわかることでもないですし、ましてやあてずっぽうや想像で言ってはダメなんです。
つまりどういうことかというと、ぼくは宝石を買う人の気持ちがいまいちよくわからないんです。
(ちなみに、「宝石」と呼べるほどのものを買ったのは人生で一度。婚約指輪&結婚指輪のときだけです。。)
いまいちわからないのなら
でも、そんな時にどうしたらいいか、ぼくは知っています。
わかるひとに聞く。
なんて当たり前だと思われるかと思いますが、実際の話、できていないことが多いのだそうです。それがもたらす結果としては、「使う人使いにくい製品を作ってしまう」とか「絶対売れると思っって開発した商品が空振り」なんてことを招いてしまっている現状があるようです。
ちなみに、「自分はその人(顧客)のことをわかっているつもりだ」というのも、罠に陥りやすい例です。
さて、「宝石に関心がある人」といえば女性。うってつけの人がそばにいます。さっそく嫁さんに聞いてみました。
聞いてみた結果
すると、まず前提として、宝石屋さんに対するイメージ。
売っているモノの価格が高いし、見た目上素人には区別がつきにくいから、だまされそうなのよね〜。
ということがあるそうです。
それを踏まえた上で、こんな宝石屋さんだと安心できるそうです。
- 人の良さそうな人
- 親身になってくれそうな人
- 誠実そうな人(ウソが下手そうな人)
イメージとしては、世話焼き好きな近所のおばちゃんとか、控えめでちょっと何か言うと焦ってしまうような男性。そんな感じになるでしょうか。もちろん宝石に対する情熱や知識は必須ですね。
ちなみに、これはウチの嫁さんの話ですが、これを5人ほどに聞いていくといろいろ見えてくるものがあるそうですよ。
どうでしょう、参考になりましたでしょうか?
では、また。(^0^)/~~ バイバイ
Facebook活用セミナーで勉強してきました。
1年生、リアル授業を受ける。
先日、Facebookの勉強会に参加してきました。弊社鈴木(大きいほう)と2人で参加です。
学生たるもの、勉強が肝心です!そこで学んだことを実践し、間違いながら人は成長していくものですなあ・・(しみじみ)

きっかけは・・講師の方の友達に
さて、きっかけは・・?といえば。
以前お付き合いがあった会社さんから、営業スタッフである鈴木のところにDMが届いたのがきっかけではあるのですが、少し説明を加えなければなりません。
そのようなセミナー案内のDMというのは、少しナナメから見てしまうというのはわたくしだけではないはずです。つまりアヤシイと・・。今Facebook勉強中の身なので、興味はあるのだけど、どうもアヤシイ。(失礼ではありますが…)
それでも、いろいろと見ていくうちに講師の方の友達の中に、自分の知り合いが4名ほどいるじゃないですか!さらにはそのメンバーを見て、「ああ、この人たちの知り合いなら内容に期待ができる」と参加を決めたわけです。
こういったところでもFacebookの効果が現れているのですね。
一番大切なのは・・「ブランディング」?
内容はといえば、とてもためになる興味深い内容でした。
「Facebookをビジネスに使う」という状況では、「一番大切なのはブランディングです」とのことでした。
はて・・・、ブランディング。とな。
この言葉、「わかっていそうでわかっていない言葉ランキング」に参加したとすれば、だいぶ上位に食い込むのではないでしょうか?
そこで、講師の方からの質問
ブランディングとはどういったことだと思いますか?」
参加者の方の答え、「価値を高めること」だと思います。
なるほど。先生もうなずく。
いや、待てよ。
実は、わたくし、以前参加した勉強会で、「ブランディングというのは、正しく期待してもらうことです」という話を聞いていたんです。
単純に「価値を高める」ということだけではなく、企業やお店が消費者の方に「どんなイメージをもってもらいたいか」を明確にして、「それをそのまま伝える」ことがブランディングなんです、と。
この部分に関しては、そちらのほうが説得力があるなあ、と感じました。
ブランディングは手法でできる??
さてさて、話を戻しまして、ではFacebookを使ってブランディングをするにはどうしたらいいのでしょう?
セミナーでは簡単なワークショップをはさみながら進行しました。
例えば、記憶に残してもらいやすい肩書きを作る場合。
- 1 自分のやっている仕事を書き出す
- 2 得意ジャンルや好きな物を書き出す
- 3 それらを組み合わせる
これでその人らしくインパクトがある肩書きになればOKとのこと。
例えば、こんな肩書きが紹介されていました。(ちなみに、実在の方です)
- スイーツ系税理士
- スカイプママ(心理カウンセラーさんです)
むむ・・なんとなく、興味をそそる気がしますね。
その前に、中身は?
ここでもう一つ重要なことを学びました。
今回の肩書きの例では「手法」ですので、「このようにすればブランディングできますよ」というやり方について習いました。
しかし、そもそも自分がどんな人間で、どう見てもらいたいかがはっきりしていなければ、これって絶対にできないことなんですね。
それがまだわかっていない場合、まずは自分と向き合うことがブランディングの第一歩と言えるかもしれませんね。
ケーススタディ
日々投稿する内容もブランディングしなければなりません。
「日記は絶対にダメです」という言葉がとても印象的でした。
ここではケーススタディでお届けします。講師の岡田さんのFacebookから引用させていただきました。
ちょっと下手なダジャレ(失礼..)みたいですが、すごく面白いですね。カツを食べたら名言をもじった一言を添えてアップするようにしているそうです。
もし岡田さんを豊田市に招いた時は、近所のおいしいとんかつ屋さんを紹介してあげたくなると思います。
でも、カツばっかりアップしていると何者かわからなくなってしまうので、お仕事のことはちゃんと書きましょうね、とのことでした。
何ごとも、ただやるだけじゃダメなんですね、考えてやらなければ。
おしまい
セミナー後は他の参加者さんと名刺交換タイムがありました。
そのあとは、一緒にいった鈴木とラーメンを食べて帰りましたとさ。
といったいろんな気づきがあったセミナーでした。

(ラーメンブランディング??)
Facebook(マーク・ザッカーバーグ)の向いている方向
こんばんは。ソーシャルマーケティング1年生です。
さて、今日は少し趣向を変えて、違った角度からお届けしたいと思います。
少し前に話題になった本に「フェイスブック 若き天才の野望」があります。

Facebookを創った天才、マーク・ザッカーバーグとFacebookの成長を描いた本です。
似た内容の、映画「ソーシャル・ネットワーク」を見た方も多いのではないかと思います。

なにをいまさら、と思われるかもしれませんが、改めて、Facebookというものが、どんな理念のもと出発したのか、わかりやすく紹介されているブログエントリーがあったので、ご紹介します。
矢野りんさんという、東京で主にWebの仕事をされている方のブログ記事で、「フェイスブック 若き天才の野望」の感想文です。
ものづくりにっぽん: フェイスブック 若き天才の野望 感想文
少し引用させていただきますと、
われらがマーク君が日々走り続ける理由。彼をやみくもに引き回す啓示は何なのか。それは「世界をうんと透明にすること」です。
と書かれており、
主体的に自分の情報をネット上で共有させる行為が定着したあかつきには、人間が世界に対して正直になり、模範的な態度さえとることが可能になるという理想。
と続きます。
100%丸ごと鵜呑みにするわけではありませんが、実体験をふまえると、あながち間違ってもいないなあ・・と感じます。
そして、みんながこの理想に共感しているせいなのか・・・、Facebookはすごい勢いで成長しています。実際、今までネットさえしたことのなかった家族がFacebookをはじめたのはびっくりしました。
また、スマートフォンやタブレットが普及してきて、ネットにつながる人の数がどんどん増えているというのも、一つの要因でしょうか。
ちょっと話がそれましたが、記事の後半に出てくる、
人間はどこまでいっても肉を通じて得た感情でしか動けないんですな。そしてたぶん物事も人が感情を通じてマジに信じた方向に動く。
なるほど、こちらもすごく興味深いです。
興味を持たれた方は、ぜひご一読ください!Facebookの見方がちょっとだけ、変わるかもしれませんよ。
ものづくりにっぽん: フェイスブック 若き天才の野望 感想文
Facebook・Twitter・ブログ どう違う?
ねえ、ねえ、私はTwitterもやったほうがいいのかな? 長女は「Facebookだけでいいんじゃない?」って言ってるけど〜。
あ、長女さんの言うとおり!おかんさんはFacebookでいいと思いますよ〜
という会話がなされたのはいつのことだったか、はて。。ずっと書こうと思っていた「Facebook・Twitter・ブログ どう違う?」をぼくなりにまとめてみようと思います。
それぞれに特徴があって、いいところ・悪いところあります。だから人によって向き・不向きがあります。また、「なにをしたいか」という目的によっても使うべきサービスは変わってきます。
それぞれの特徴まとめ
まず、個人的に感じでいるそれぞれのサービスの特徴をまとめましたので、ご覧ください。
「個人的に」という部分がポイントで、感覚的なことももだいぶ含まれています。あと、歯切れの悪い表現が多くて申し訳ありません。。

それぞれ、少し補足します。
情報の貯まり方
実は受け売りですが、これは結構重要です。
みていただくとわかりますが、ブログだけが「ストック型」です。どういうことかと言うと、ブログは情報を整理して貯めていくことができるサービスだということです。
それに比べ、FacebookやTwitterは「フロー型」といって、新しいものが次々に更新されるので、どんどん流れていくイメージです。ですので、過去に遡って情報を探すのにはあまり向いていません。
ブログはずいぶん前からあるので古いイメージがあるのかもしれません。しかし、これを見ていただくとわかるように、FacebookやTwitterではできない「貯めて・整理して・伝える」ということができるサービスなんです。
よくある例として、ブログに書いて、Facebook、Twitterで拡散というのは常套手段ですね。(あ、自動化はあまりオススメしません)
発進力
貯まり方で書きましたが、それぞれ役割が違うので一概には言えませんが、瞬間的な発進力で言うとTwitterが優れています。話題性のある内容は、「RT(アールティ)」と呼ばれるリンクボタン一つで、どんどん拡散されていきます。
開かれ具合
ブログは広く開かれています。検索をすれば誰でも辿り着くことができます。
Facebookは基本的に友達や知り合い同士のつながりです。設定によりますが、情報を友達のみにしか見れないようにしているケースがよくあります。(※不特定多数に発信することも可能です)
Twitterはどちらかというと開かれ気味。プライバシー設定をしていなければ誰でも見れるのですが、検索にひっかかりにくいという意味で、開かれ気味。
伝わる早さ
あ、発進力の項目とたいして変わりませんね(^_^;)
つながり度
それぞれ、つながる機能をもっていますが、やはりFacebookのつながる力は強いと言わざるを得ません。
ブログは「自分からブログを見に行って、コメントをする」という行動になりますが、FacebookやTwitterは待っていても流れてきます。特にFacebookは、その人が欲しいと思う情報を的確に出すような仕組みを取り入れているようです。
実名登録
ブログやTwitterの場合は、実名の方が少ない印象でしょうか。有名人や、経営者さんなどは実名が多いですが、一般の方は名前を伏せていることが多いと思います。
しかしFacebookは圧倒的に実名が多いです(顔写真も)。ネットに個人情報をさらす怖さはありますが、逆に素性が知れているので、誹謗中傷や炎上が起こりにくいという事実もあります。
また、設定によって、プライバシーを保護できる仕組みも備えています。これについては、以前書きました。
例えばこんな使い方
と、上記のことをふまえると、それぞれサービスにあった使い方ができてくるかと思います。冒頭でもあったように、おかんさんの場合はTwitterはやらずにFacebookだけでいいという判断をしました。
理由としては、
- 実名や顔出しもある程度問題ない
- 地元の人たちと濃いつながりを持ちたい
- すでにお知り合いがFacebookをやっている
といったことがあると思います。
それぞれの特徴をつかんで、目的にあったサービスを選びたいものですね。